ホームページは自作か、制作会社に頼むべきか
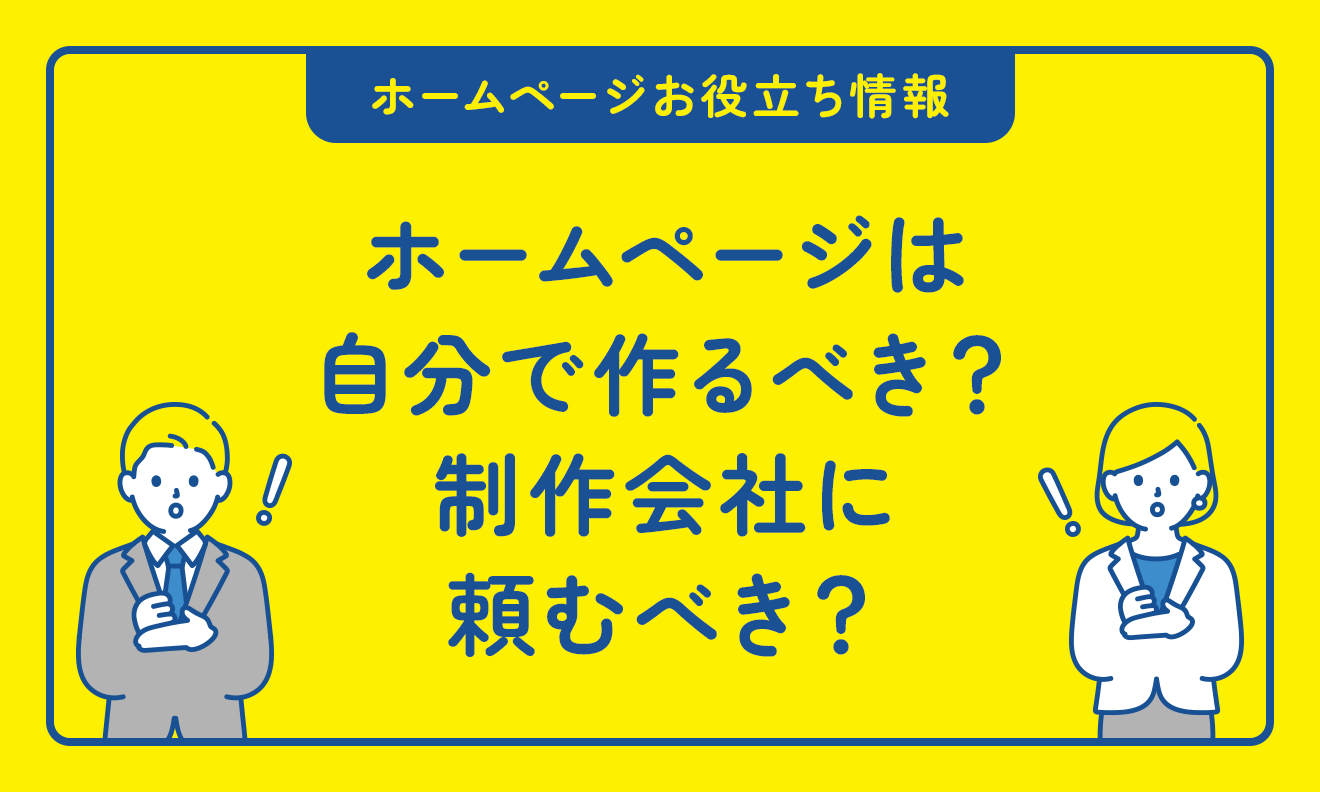
先日、とあるサイトで「ホームページは自作か、業者に頼むべきか」で悩んでいる方の投稿を見かけました。
コメント欄にはそれぞれの経験からさまざまな意見が飛び交い、一見するとどれも一理あるように見えるものでした。
ただ、そうした議論の中で専門的な視点が十分に示されていないようにも感じました。
そこで本記事では、ホームページ制作のプロとして、自作する場合のメリット・デメリットを中心に整理しつつ、最終的に「どちらを選ぶべきか」考えるうえで役立つ知見をまとめています。
目次
ホームページを作る前に意識しておきたいこと
ホームページを持つ目的は、実は人それぞれです。
- 企業やお店の“顔”として信頼を得たい
- 商品・サービスをわかりやすく伝え、問い合わせや来店につなげたい
- 採用や求人活動のツールとして活用したい
- オンライン経由で売上アップを狙いたい
これらを実現するには、ホームページで「誰に」「何を」見せて、「どう感じてもらい」「どう行動してもらうか」を設計しなければなりません。
ところが、ホームページ制作に知見がない方が自作する場合、こうした“目的設定”や“導線設計”が曖昧なまま進めがちです。
その結果、「全然問い合わせが来ない」「自分以外ほとんど見ていない」「更新も止まって古い情報のまま……」といった、“作っただけ”の状態になりやすいのです。
ここからは、ホームページを自分で作る場合のメリットとデメリットを、プロの視点を交えながらわかりやすく解説します。
まずは「自作ツールでできること」と「実際にやってみるメリット」から順に見ていきましょう。
1. 自作ツールの選択肢と特徴
近年、専門知識がなくてもホームページを作れるサービスが豊富になりました。代表的なものは以下の通りです。
| ツール | 特徴 |
|---|---|
| STUDIO | 直感的操作でデザイン性の高いサイトを構築可能。クリエイティブ業界にも人気。 |
| Wix | 予約・EC・ブログなど多彩な機能が追加できる。一通りのことはここで完結。 |
| ペライチ | 1ページ完結型のLP(ランディングページ)に強い。素早く形にしたい人向け。 |
| WordPress | 世界中で使われるCMS。拡張性に優れるが、やや知識や管理の手間が必要。 |
共通するメリットとして、初期費用を抑えつつ短期間で公開できることが挙げられます。
ただし、後述のデメリットで解説するように、カバーしきれない課題も多いです。
2. 自作ホームページのメリット 〜「試しに作ってみる」のハードルが低い〜
1) コストが低い
制作会社に依頼すると、数十万円〜数百万円の費用がかかることもありますが、自作ツールなら無料または月額数千円程度。とりあえず名刺代わりにサイトを作りたい場合には、大きなメリットです。
2) 好きなタイミングで更新・修正できる
営業時間の変更、キャンペーン情報の追加などを、思い立ったときに即反映できます。外注の場合、都度やり取りや追加費用が発生することもあります。
3) 自社の強みを改めて整理できる
ホームページを作る過程で、「うちのアピールポイントは何だろう?」「誰をターゲットにしているんだろう?」と考える機会が増えます。これはビジネス全体を見直す良いきっかけにもなります。
4) Webスキルが身につく
画像の加工や文章の書き方、SEOキーワードの選定など、実際に手を動かすことで基礎的なWeb知識が吸収できます。今後の運用にも活きてくるでしょう。
プロ視点: 「自分で作りながら勉強したい」「更新頻度が高い」「まずは試しに簡易サイトが欲しい」といったケースでは、初期段階の自作は有効です。ただし、それが本当に“成果”につながるかは次のデメリットを要確認。
3. 自作ホームページのデメリット 〜“見落としがちな視点”と“成果への壁”〜
1) デザインやUI/UXの統一感が不足しがち
プロが意識するポイントは、単なる「見た目のカッコよさ」ではなく、ユーザーの操作性や企業イメージとの統一感です。色の選び方、文字のサイズや行間、写真の質とレイアウト、余白の取り方ひとつで印象は大きく変わります。
たとえテンプレートを使用したとしても、実はそれだけでデザインやUI/UXが自動的に担保されるわけではありません。
テンプレートはあくまで「ひな形」に過ぎず、配色やフォント、写真の選定や配置、余白の取り方などをしっかり調整しないと、結果的に統一感を欠いたまま中途半端な仕上がりになってしまいます。
「テンプレートを使えば大丈夫」と思い込んでしまうと、本来は必要なブラッシュアップを見落とし、最終的には訪問者から「ここに依頼して大丈夫かな?」と疑念を抱かれるリスクを高めてしまう点には注意が必要です。
2) SEOや導線設計が不十分
- ターゲットとなる検索キーワードは何か?
- サイト内の構造はクローラに正しく認識されているか?
- 導線(どのページから問い合わせフォームへ誘導するかなど)は最適化されているか?
こうした要素が欠けると、「せっかく作ったのに検索に出てこない」「訪問者がどこで離脱しているかわからない」という状態に。
3) マーケティング視点の不足
ホームページは“オンラインの営業マン”です。トップページから会社概要、サービス案内、問い合わせとスムーズに誘導できる構成が必要ですが、知見が不足している場合はどうしても「作って終わり」になりがち。
プロは“売れる仕組み”や“信頼を高める仕掛け”をサイト全体で設計します。そこにはコピーライティングや心理的アプローチも含まれます。
4) 時間と手間を取られ、本業を圧迫
慣れないツール、画像編集、文章作成……思っていた以上に作業時間がかかります。その分、本業の売上につながる活動に時間を割けなくなるのは大きな機会損失です。
5) 結局、形だけになりがち
「公開してはみたが、全然アクセスがない」「問い合わせも来ない」など、“放置サイト”化するケースは少なくありません。それはホームページ自体が問題というより、“目的設定”と“戦略”がなされていないからです。
4. プロに依頼すると何が違うのか?
ここからは、ホームページ制作をプロに依頼した場合のメリットや、制作会社、クラウドソーシング、フリーランスへ依頼した場合について、さらに深掘りしていきます。
自作と比較した際の決定的な違いを理解することで、より自分のビジネスに合った選択ができるようになるはずです。
4-1. プロが重視する「成果につながる設計」
ホームページ制作に知見がない方が見落としがちな要素として、以下のような視点があります。
コンテンツ戦略
どのような情報を、どのページに、どんな順序で配置するか。
→ 訪問者が知りたい情報を適切に配置することで離脱率を下げ、問い合わせにつなげやすくします。
UI/UX設計
ボタンやメニューの配置、文字サイズ、余白の使い方などのユーザビリティ。
→ 訪問者がストレスなくページを回遊し、目的のアクション(購入、問い合わせなど)に導きやすくなります。
コピーライティング
商品・サービスの価値や魅力を分かりやすく伝える言葉選び。
→ 「このサービスなら安心して利用できそう」と感じてもらうための心理的アプローチも含まれます。
プロは、デザインや写真素材の選定だけではなく、“売れる仕組み”や“信頼を高める仕掛け”を総合的にプランニングします。
4-2. 時間と手間を大幅に削減できる
ホームページ制作には、思った以上の時間と手間がかかります。ツールの操作やデザインの調整、画像素材の用意、コピーライティングなど……。
プロに依頼すれば、これらを任せられるため、本業に集中できるのは大きなメリットです。
最初の要件定義や素材提供などのやり取りは必要ですが、それ以上の細かな作業は基本的にプロ側が進めてくれます。
4-3. アフターサポートや修正がスムーズ
- 更新方法や管理画面の使い方を教えてもらえる
- 不具合が起きた際に迅速に対応してもらえる
- 新たな機能追加やデザイン変更の相談がしやすい
こうした継続的なサポートは、特に初心者にとって心強いものです。
4-4. 集客やマーケティングの導線まで含めた提案
プロはホームページを“作る”だけでなく、“運用して成果を出す”までを視野に入れます。以下のような具体的なアドバイスが期待できます。
- SNSとの連携方法(どんな投稿をすると良いか、更新の頻度は?)
- ブログやコンテンツマーケティング(定期的に記事をアップし、検索流入を増やす)
- リスティング広告やSNS広告の活用(どのタイミングで広告を打つか)
これらは“ホームページを機能させる”うえで非常に重要な要素。自作だと、なかなかここまで手が回らないケースが多いでしょう。
5. クラウドソーシングの落とし穴と依頼時の注意点
「プロに依頼」と聞くと、まず検討されやすいのがココナラやランサーズといったクラウドソーシングかもしれません。確かに、予算を抑えながら外注できる便利な方法ですが、以下のような構造的リスクがあります。
5-1. スキルや経験がまちまちで、ヒアリング不足になりがち
自身で仕事を獲得できない方や駆け出し、副業の制作者が多く、デザインやコーディングはできても、マーケティングや戦略設計が不十分なケースが多いのが実情です。
さらに、クラウドソーシングの応募段階で十分なヒアリングがなく、依頼内容の表面だけを読んでいきなり提案を受けることが多いです。
このため、製作者を提示価格やデザインだけで選定してしまうことが多く、いざ制作が始まると企業やサービスの本来の課題や目標が十分に共有されず、最終的に「見た目だけが良い」サイトに終わってしまうことがあります。
5-2. “○円で○ページ”といった表面的な交渉
本来は事業内容やターゲットの理解・競合調査・適切なページ構成や機能の設計などが必要ですが、価格競争によって「5ページ作成で○円」といった形式ばかりが先行し、肝心の戦略提案や要件定義が省かれやすいのが現状です。
さらに、安さを求めるあまり、依頼者はより低価格な制作者を選びがちで、適切な予算が確保できず、質の高い提案や戦略設計を期待しにくいというデメリットがあります。
5-3. 納品後のサポートや改善が期待しづらい
納品後の修正に追加料金がかかったり、そもそもやり取りの継続が難しいことも少なくありません。
長期的なパートナーシップを築く意識が薄いため、運用しながら改善を重ねるという本来のサイト運営が実現しにくいのです。
6. 制作会社に依頼した場合のメリットと注意点
ホームページ制作を外注する際、制作会社に依頼するという選択肢も当然あります。複数の専門スタッフが在籍し、クオリティの高いデザインや開発を期待できるケースが多いです。しかし、以下の点に留意しておきましょう。
6-1. 組織体制と専門分野の分業
制作会社には、ディレクター、デザイナー、プログラマー、マーケターなどが分業で配置されている場合が多く、それぞれの専門知識を集結しやすい環境があります。
クライアントの要件をしっかりヒアリングし、サイトマップやデザイン案を提案し、必要があればシステム開発や保守運用まで一貫してサポートしてくれるケースもあります。
- 多角的なアプローチで、デザインと機能を両立しやすい
- 大規模案件や複雑な要件に対応できる
- プロジェクト進行が体系立っており、品質管理もしっかりしている
6-2. 費用が高くなりやすい
人件費や会社の運営コストがあるため、制作会社の見積もりは相対的に高くなる傾向があります。200万円〜600万円の案件が主流となり、予算に限りがある事業者にはハードルが高い場合もあります。
6-3. すべての制作会社が“プロフェッショナル”とは限らない
会社組織であっても、技術力やマーケティング戦略が不十分なケースは意外と多いです。
中には「十分な検証を行わずとりあえずブラウザで見れていればOKとそのまま納品して終わり」「毎月数千円の保守料を取っているが実際には問題が表面化しない限り何もしない」など、成果には結びつかないまま高額な費用を請求する会社も存在します。
ホームページ制作の実績や得意分野、運用支援の有無などを事前に確認することが重要です。
- 営業担当と実務担当が異なるため、打ち合わせ時にうまく要望が伝わらない可能性がある
- 大手案件にリソースを割かれ、中小規模案件のサポートが手薄になるケースも
- 運用開始後の保守や解析・改善提案をせずに、納品で終わる会社がある
7. 実力あるフリーランスに頼むメリット
制作会社に依頼すると、どうしても費用は高くなりがちです。だからといってクラウドソーシングで激安案件を探すのも不安——そんなとき、実力あるフリーランスに依頼するのは良い選択肢となります。
- 費用を比較的抑えつつ、戦略・デザイン・開発を総合的に任せられる
- 柔軟なやり取りができ、個別の要望や相談に親身に対応してもらえる
- マーケティングやブランディング視点まで踏み込めるフリーランスも存在
特に、自力で集客ができているフリーランスは、自分自身がWebマーケティングを理解している場合が多く、サイト制作以外にもノウハウを提供してくれることがあります。
8. まとめ:自作か外注か、判断のポイント
●自作が向いているケース
- とりあえず最低限の情報を掲載したい
- 予算に極力お金をかけられない
- 学習も兼ねて自分で作業したい
- 小規模でページ数が少ない
●プロ(外注)が向いているケース
- 集客や売上アップ、ブランディングが主目的
- 多ページ構成や機能拡張(EC、予約システムなど)を見据えている
- デザインやユーザビリティにこだわりたい
- 本業に集中したい
- 成果につながる長期的なパートナーを探している
弊社TNGC graphicsは、フリーランスならではの柔軟な対応とプロのノウハウを兼ね備え、ホームページ制作全般(デザイン・コーディング・CMS構築)、Web集客の戦略設計(SEO、SNS活用、コンテンツマーケティング)、既存サイトのリニューアルや改善提案などを得意としています。
「自作しているけど、このままでいいのか不安……」
「ホームページで集客したいが、何から手をつければ?」
といった方は、ぜひお気軽にご相談ください。
見積もり・相談は無料です。あなたのビジネスに合わせた最適解を一緒に見つけましょう。
自作と外注、それぞれのメリット・デメリットをしっかり踏まえ、あなたの目的にぴったり合う方法を選んでくださいね。
この記事の執筆者

谷口正頼
デザイン業界に身を置いて二十年余り、独立して十数年になります。大学では社会福祉を専攻しておりましたが、世界的なデザイナー中島英樹の作品に触れ、デザイナーに憧れを抱いていたものの、デザイナーって専門の学校出てなければなれないのではという疑問を知り合いの先輩デザイナーにぶつけてみると「学校出てなくてもなれるよ」の一言で目から鱗。独学で猛勉強してデザイナーに。グラフィックデザイン会社やウェブ制作会社を経験したのち、フリーランスとして独立。
